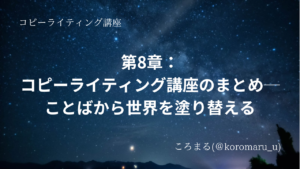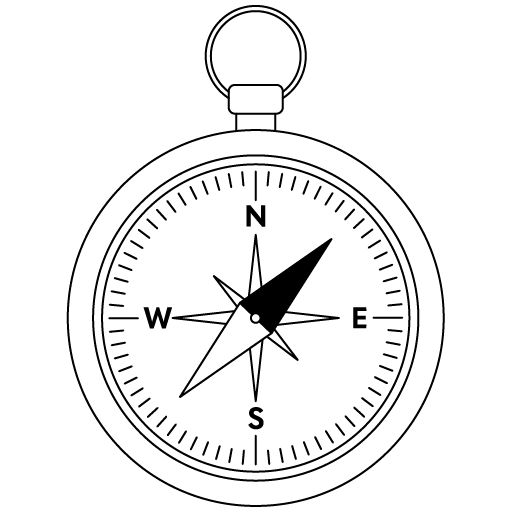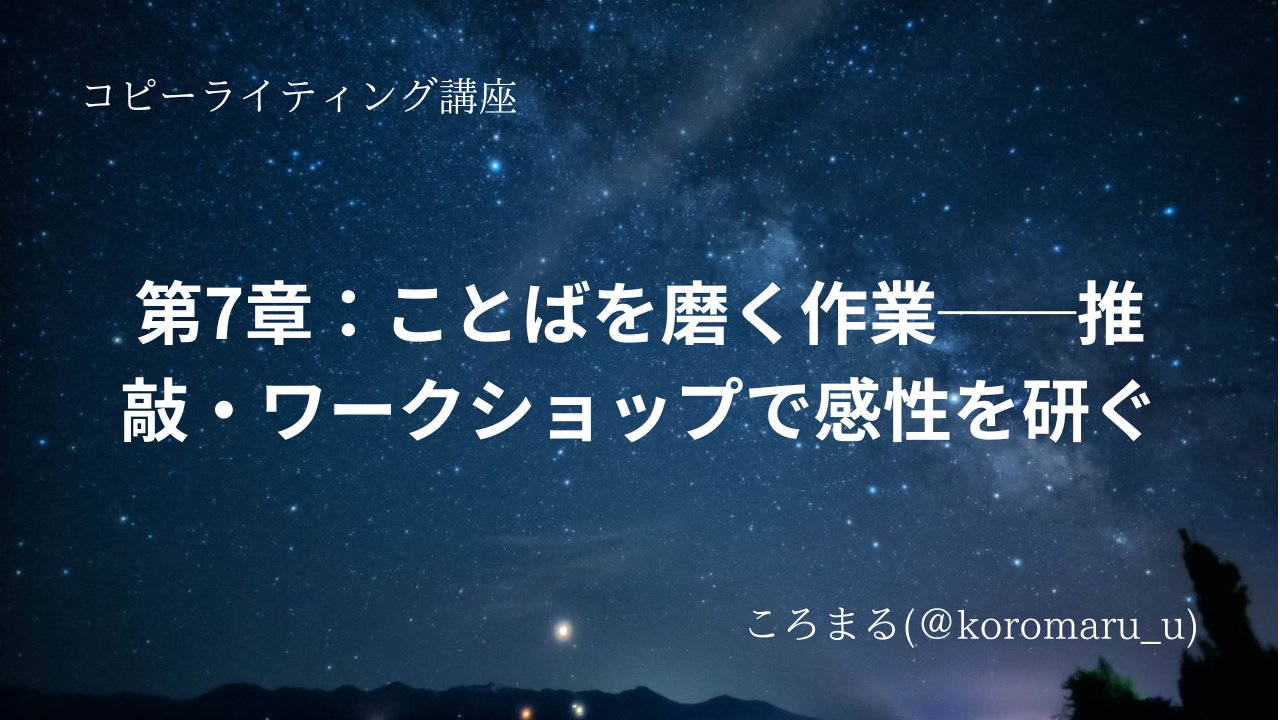文章を書くことは、いわば読み手に自分の頭の中をのぞかせる作業ともいえます。
書いているときは「これで伝わる」と思っていても、読み返すと「あれ? ここの表現、くどいな…」「ここは曖昧かも…」と引っかかる点が見つかる。
では、この“引っかかり”をどうやって解消し、さらに文章を良くするか。
その鍵になるのが“推敲”や“ワークショップ”という方法です。
第6章まで、“コピーライティング”というテーマを軸にさまざまな場面を見てきました。
ヘッドラインやSNS向けの短文、LPの構成、そしてブランドのコンセプトづくり。
どれも書きあがった段階では「よし、できた!」と思いやすい。
でも、そこからもう一歩踏み込んで磨きこむと、“本当に読者の心にすっと馴染む文章”へ伸びる可能性があるわけです。
逆に、磨き込まれていないコピーは、人の心の奥底には響きづらいんですよね。
だからこそこの推敲やワークショップという手順はかなり面倒だけど不可欠なのです。
本章では、“磨き”を具体的にどんな手順でやると効果的なのか、“ワークショップ”というスタイルをどう活用すれば良いのか、そしてどうやって自分の文に“気づき”を生かすのかを考えます。
もしかしたら、書いている途中や書き終わりで「すでに十分だ」と思い込んでいませんか?
頑張っている時点で褒めてあげたくなりますが、人の心を震わせるには不十分なケースがとても多い。
それを、もう何度も見直して“もうちょっと良くなる”と感じられるのが、推敲の魅力なんですよね。
実はプロのコピーライターほど、仕上げに多くの時間を割いています。
最初のドラフトを書くのは早いけど、その後の微調整やことば選びにじっくり向き合って、あっちを削って、こっちを加えて、時にはごっそり書き直す。
そうやって“完成形”を磨いていく。
では、プロではない素人には無理なのか。というとそんなことはありません。
誰でも同じように“磨く”プロセスを踏めば、文章は劇的に変わります。
あなたのことばがどこまで伸びるのか、追求していきましょう。
推敲テクニックの深堀り

まずは基本的な“推敲とは何か”を考え直してみましょう。
推敲とは、文章を一通り書きあげたあとに見返し、余計な部分を省いたり、足りない説明を補ったりする工程ですが、それ以上に“感触を確かめる”行為でもあるのです。
自分で書いておきながら、後で客観的に読むと「あれ? こういう意味に取られるかも」と気づくことは多い。
そこで修正を入れていくわけですね。
たとえば、料理を作る時にも、
出来上がった料理を試食して「なんかしょっぱいから塩加減を減らそう」とか「もうちょい砂糖を入れた方が良さそう」と微調整しますよね。
文章でも同じように“もう少し削ったほうが見栄えがいいかな”“いや、ちょっと説明が足りないな”と確認する。
こうして推敲は、書いた文章を“本当にちょうどいい味”へ近づける作業とも言えます。だから重要なんですよね。
余分を削る“減法”×足りない要素を補う“加法”──文章を引き締め華を添える
文章を研ぎ澄ますとき、“ことばを削る”ことがいちばん即効性があります。
熱の入った原稿には、形容詞や副詞がどっさり詰めこまれているケースが多いじゃないですか。
「超絶すごくビックリするほどに明るい未来が見えます!」と詰めこんでも、むしろ読者は「あ、なんか勢いだけ?」と逆に冷めたりするわけです。情報商材のレターにありがちですね。
だから“不要かな”と思える語を大胆に削ってみる。この場合だと「超絶/すごく/ビックリするほど」はどれか1つで良いですよね。
削るのは怖いですが、「伝えたいことは読まれなければ伝わらない」わけなので、勇気を出しましょ。
すると文が引き締まって、読みやすくなる例は非常に多い。
本当に伝えたいエッセンスだけ残るように文章をスリムにすれば、結局読者は“あ、こういう意味だよね”とダイレクトに理解しやすい。
いわば減法は“なぜそれを書いたのか”を改めて自分に問いかける行為とも言えます。1回目に書くときに思いのままに書き連ねることは全くもって悪ではありません。ただ、文章は伝えるためにあるものなので、引き算は必須なのです。
一方、“なにか足りないな”と感じる箇所に適切なフレーズを加える「加法」も大事。
単純に文字数を増やすというよりも“補完する”意識での加筆がポイント。
「美味しい飲み物です」だけでは漠然としすぎるなら、「甘さ控えめだけど余韻が残る、きれいな後味です」と一文足す。
これで読者は「なるほど、甘すぎないのね」とイメージをしっかり抱けるわけです。
要は、減法と加法を両方活用して“必要なところは補い、不要な装飾は省く”が基本姿勢。
伝えたいことを伝えきるために必要十分な文にする必要があるわけです。
今すぐ行動!タスク
- あなたが最近書いた文章の中で、形容詞・副詞を削ってみてその前後を比べてみてください。
- また、どこか“説明不足”だなと思う箇所に一文だけ加筆して、読者が想像しやすい状態になるかチェックしてみましょう。
小さな変化で大きく印象が変わることに気づくはずです。
専門用語の扱い方──読者のリテラシーに合わせる
専門的な分野を語るとき、避けられないのが専門用語ですよね。
これをすべて無くしてしまうと説明が正確じゃなくなるし、多用すれば「難しそう…」と敬遠されるかもしれない。
結局、ターゲットや媒体に合わせてバランスを取るしかないわけです。
初心者向けなら、なるべくかみ砕いた一般用語を使ったり、括弧書きで一瞬補足を入れたりする。
専門家向けなら逆に遠慮なく専門用語を並べてOK。
この判断をする際は“誰に読んでほしいか”が明確になっているかが鍵です。いわゆるターゲット・ペルソナですね。あなた自身がその立場にたった時に、すっと入ってくる文章でないと伝わりません。
今すぐ行動!タスク
- あなたがもし専門的な内容を伝えるなら、「初心者向け版」と「専門家向け版」の2種類の文章を試しに書いてみてください。
- それぞれでどんな用語を省く or 補足するか意識すると、ターゲットに合わせた推敲が見えてきます。
リズムと読点──音読して心地よさを調整する
推敲段階で、自分の文章を声に出して読んでみると「あ、ここ苦しい…」と感じるポイントが浮かびやすいです。
読点の位置がおかしいとか、同じことばを何度も使いすぎてテンポが悪いとか、音読すると客観視しやすいんですよね。
たとえば、長い一文を敢えて区切らずにテンポよく流したいなら読点を控える。
逆に、じっくりゆっくり感を出したいなら、区切りを増やして、読者が休みやすいリズムを作るなど、音楽的な発想で文章を“演出”する感覚です。
媒体によっては改行も効果的ですし、可能なら太文字や斜め文字、文字のカラーなどで意図的にリズムを変えることもできます。
今すぐ行動!タスク
- 5〜6行程度の短い文章を用意し、声に出して読んでみて読点や改行を調整してみましょう。
- Before/Afterで見比べると、どこが読みやすくなった or テンポが変わったかがわかりやすいはずです。
実例研究とケーススタディ
ここでは、実際の成功例や失敗例を見ることで“推敲”の威力を体感しましょう。
小さな表現差で爆発的反応──微修正が“売れ行き”を劇的に変える
セールスコピーの世界では、わずかなフレーズ変更だけで売上が数倍に伸びる事例が多々あります。

たとえば、小説『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』の例では、初版の帯コピーを変えただけで大幅に売上が伸び、映画化にも繋がったというエピソードがあります。
最初の帯では「彼女の秘密を明かす」みたいな内容だったのを、読者がSNSに書いた感想(「電車で読んで大号泣」など)を載せるスタイルに切り替えたところ、爆発的に共感を呼んだ。
こうした“微修正”が大きな影響を与えるのは、言語表現が読者との距離を一気に縮めるからです。
今すぐ行動!タスク
- あなたの書いた紹介文やキャッチコピーを1つ選んで、その商品やコンテンツを“第三者の声”を引用する形で書き直してみてください。実際の声があるのがベストですが、なかったら近い人にお願いしてみてください。
- 読者が自分の体験や感情として共感しやすくなるはずです。
ダメ見本から学ぶ“地雷フレーズ”──使うだけでマイナス効果
一方、“煽りすぎ”や“差別・侮辱的”なことば選びは地雷になりやすいので注意が必要。
昔流行った「怠け者のあなたでも稼げる!」みたいなコピーも、今だとかなり厳しいですよね。
影響力がある人がこういうコピーを用いて拡散されると「読者を舐めてんのか」と炎上するリスクもある。し、当然スルーされる可能性もかなり高いです。
結局、“推敲”でそれに気づけば回避できるわけです。
「あれ、これって一部の読者を馬鹿にしてるように聞こえるかな」と自分でチェックするだけでリスク回避できます。
今すぐ行動!タスク
- 自分が最近書いた or これから書こうと思うコピーで、「他人から見て不快に思われる可能性」があるかどうかチェックしてみてください。
- もし微妙なら、その箇所を言い換える(煽りを和らげる、差別的な文言を避けるなど)形で書き直し、読者に与える印象をもう一度見直してみましょう。
商品名・キャッチ変更で価値上昇──リブランディングの成功パターン
推敲は文章全般だけでなく、商品名やプロジェクト名のリブランディングにも効果を発揮します。
“男前アイロン”に名前を変えただけで売上が跳ね上がった老舗メーカーの話などは有名な例ですよね。
従来の「無難な名前」から、一歩踏み込んだ印象的な名前に変えれば、ユーザーが「おもしろそう」「気になる」と思ってくれることはよくあります。
今すぐ行動!タスク
- あなたの扱う商品の名前やサービスの名称を、あえて2~3パターン変更してみてください。
- どれが一番印象に残るか、周囲の反応を聞き比べると、自分の思い込みと違う結果が出る可能性もあります。
実践ワーク:リアルタイム推敲
“わかったつもり”になりやすい推敲を、本当にやってみると意外と新鮮な発見があります。
ここでは手軽にできる3つのワークを紹介するので、ぜひ試してみてください。
声に出して読む──舌が絡む部分は伝わりにくいサイン
最初は簡単だけど超強力な方法。
音読してみると、どこで噛みそうか、どこが回りくどいかが如実に出てきます。
声に出して読みづらい文章は、読者も脳内を巡らせることを拒否します。
今すぐ行動!タスク
- 1分以内で読める短文を用意し、声に出して読む→噛みそうな箇所や苦しいところをチェック→読点や語順を微調整して、もう一度声に出してみる。
- Before/Afterで印象がどう変わるか体感してみてください。
第三者のフィードバック──視点を変えてコピーを磨き上げる
自分で書いていると、自分の頭の中の前提を入れ込みすぎる場合があります。
言語化しないと伝わらない部分を、「皆知ってるでしょ」という前提で書いてしまうのは、知識がある人ほどやりがちなことです。
他人に見せて「ここ分かりづらい」「ここ好き」など率直な感想をもらうと、書き手が気づかなかった誤解のポイントが発見できる。
今すぐ行動!タスク
- 書き上げた文章を、最低1人に見せて「遠慮なくダメ出しして」と頼んでみてください。
- 指摘された箇所を受けて推敲すると、自分では気づけなかった修正点を補える可能性が高いです。
Before/Afterで推敲成果を可視化──変化が分かるとやる気が続く
書き直し前の文章を“Before”、書き直し後を“After”として並べると、推敲が何を変えたのか一目瞭然です。
“ここで形容詞を1つ削った”“ここで順番を入れ替えた”など微調整がわかると、自分の推敲パターンが見えてくる。
推敲パターンが蓄積されていくと、今後コピーや文章を書くときの一発目の質が段違いで変わってきます。それが実力になっていくわけです。
自分が書きたい文章と、読者に伝えたい文章の差を蓄積させていく感覚です。
今すぐ行動!タスク
- 100〜200文字程度の文章をBefore/After形式で保存し、どこを変えたか(削った単語、変えた語尾など)をメモしてみてください。
- それらの記録を積み重ねていくと、今後の推敲がスムーズかつ的確になっていきます。
第7章のまとめ

“ことばを磨く”推敲の工程は、地味なようでいて想像以上に成果が大きい。
書くだけでも一苦労なのに、
さらに何度も直すとかめんどくさ…
と思う人も、実際にやってみると「あれ、こんなに変わるんだ」と快感を覚えるはず。中毒になりかねません。
そして経験値の蓄積は凄まじいです。
たとえ手間でも、ちょっとの差が読者の受け取り方を激変させるのがコピーライティング。
しかも、その推敲能力はやればやるほど身につき、“書く→直す”のサイクルが速くかつ正確になるというメリットまである。
最初は“どこを直せばいいかわからない”こともあるかもしれませんが、今回の方法を通して自分のアラ探しや第三者の目を用いれば、少しずつポイントが見えてきます。
次の第8章でいよいよ本講座の締めくくりとして、これまで学んだ要素をどうまとめ、どう行動に移していくかを総合的に整理します。
推敲が終わり、リリースした文章が“読者の前”でどんな反応を巻き起こすか。
そこまで想像して書くのがコピーライティングの醍醐味だと、改めて感じていただけると思います。